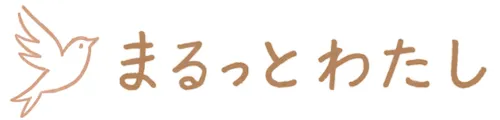ゼロサムを超えて──お金と文化の循環
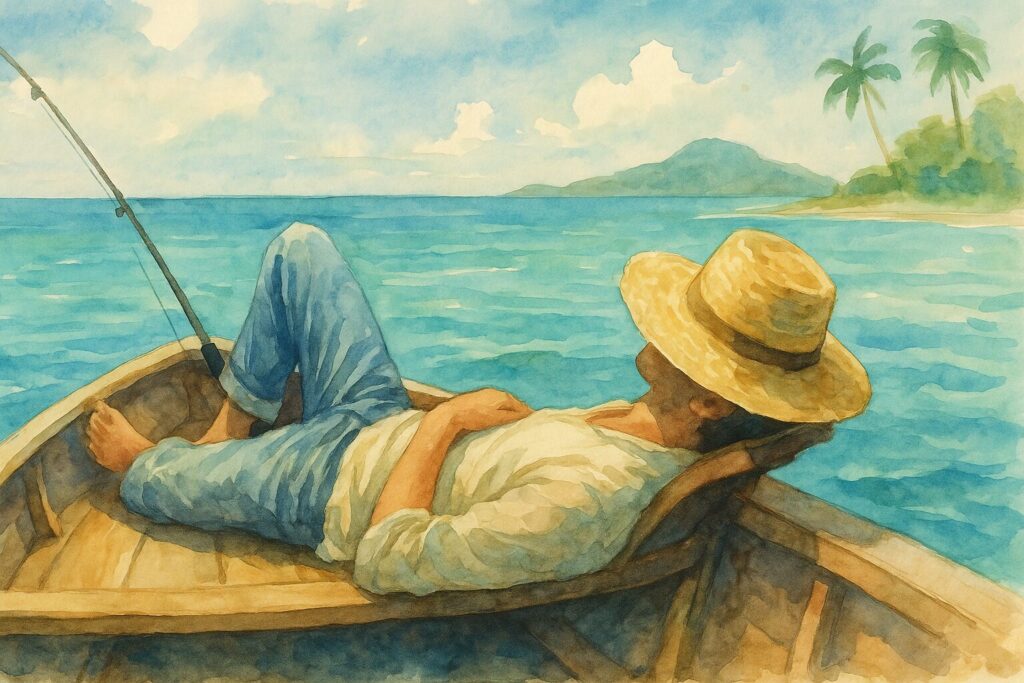
「誰かが得をすれば、自分は損をする」
そうしたゼロサム(損得の総和はゼロ)の思考が、いかに人類を縛りつけてきたことか。
もしこの世が本当にゼロサムのみに支配されていたなら、文明はここまで発展していない。
欠乏意識と溜め込みの連鎖
人類の歴史は「欠乏」との戦いから始まった。
獲物を取り合い、作物を飢饉に備えて蓄え、富を囲い込む。
そうした積み重ねが、心の奥底に「足りない」という思い込みを刻み込んできた。
足りないと思うがゆえに、必要以上に溜め込む。
だが溜め込みは必ずどこかを干上がらせ、社会全体の富を痩せさせる。
経済は水の循環である
経済の原理は、水の循環に似ている。
流れていれば皆が潤う。せき止めれば下流は渇水し、やがて水そのものが濁り腐る。
富を流す仕組みは、単なる数字の操作ではなく、人の心に安心をもたらす装置でもある。
安心からこそ、人は与え合う存在となる。
溜め込んだものをひっぺがすことは奪うのではない。
滞留を再び流れに戻すための作業である。
縄文と南の島の知恵
縄文の社会には、戦の痕跡がほとんどないと言われる。
また南の島々では、果実や魚が絶えず手に入るゆえに、倉庫や貯蔵の文化すら育たなかった。
常に「足りる」が保証された社会には、欠乏も争いも存在しなかったのだ。
一方、弥生以降の農耕社会では、余剰を管理する権力者が現れ、格差と争いが生まれた。
欠乏意識が制度に組み込まれた瞬間である。
富を溜め込む者が称賛される歪み
現代においては「富を持つ者」が称賛される。
だが実際は、滞留をつくり出す者ほど「成功者」と呼ばれている。
バフェットのような投資家は典型だろう。
お金でお金を増やすに過ぎず、循環を止める仕組みに加担する。
本来讃えられるべきは、流れを生む者、人を支える者であるはずだ。
資本主義の限界とシェア文化
資本主義はもともと「投資→生産→循環」という流れを基盤にしていた。
しかし今や「投機→吸い上げ→滞留」へと変質した。
溜め込み型から循環型へ、発想を切り替えねばならない。
そのヒントはシェア文化にある。
ニコ動やYouTubeが示すもの
ニコ動やYouTubeで文化が花開いたのは、まさにシェアゆえだ。
「歌ってみた」「踊ってみた」「演奏してみた」
──誰かの作品をリスペクトし、遊び、共有し、さらに発展させていく。
著作権を過剰に振りかざすことなく、技術や作品を分かち合ったからこそ、新しい創造が連鎖した。
独占は流れを止め、シェアは流れを増幅する。
経済においても文化においても、答えは同じだ。
ゼロサムを超えて
欠乏意識に囚われ、溜め込む社会はやがて痩せ衰える。
循環を取り戻す社会には、安心が芽生え、与え合う文化が育っていく。
ゼロサムを超えて──
お金も文化も、流れることによって豊かさを増していくのだ。
豊かに生きたいあなたへ
与え合う社会に変わるためには、まずは、ひとりひとりが安心できるようになることが大事です。
そして、安心感は、外側ではなく、自分の心が作り出しています。
10日間メール講座では、安心感を生み出すためのヒントを伝えています。
もっと豊かに生きたいなら、ぜひ一度読んでみてください。
▼無料メール講座の詳細はこちら(画像をタップしてください)
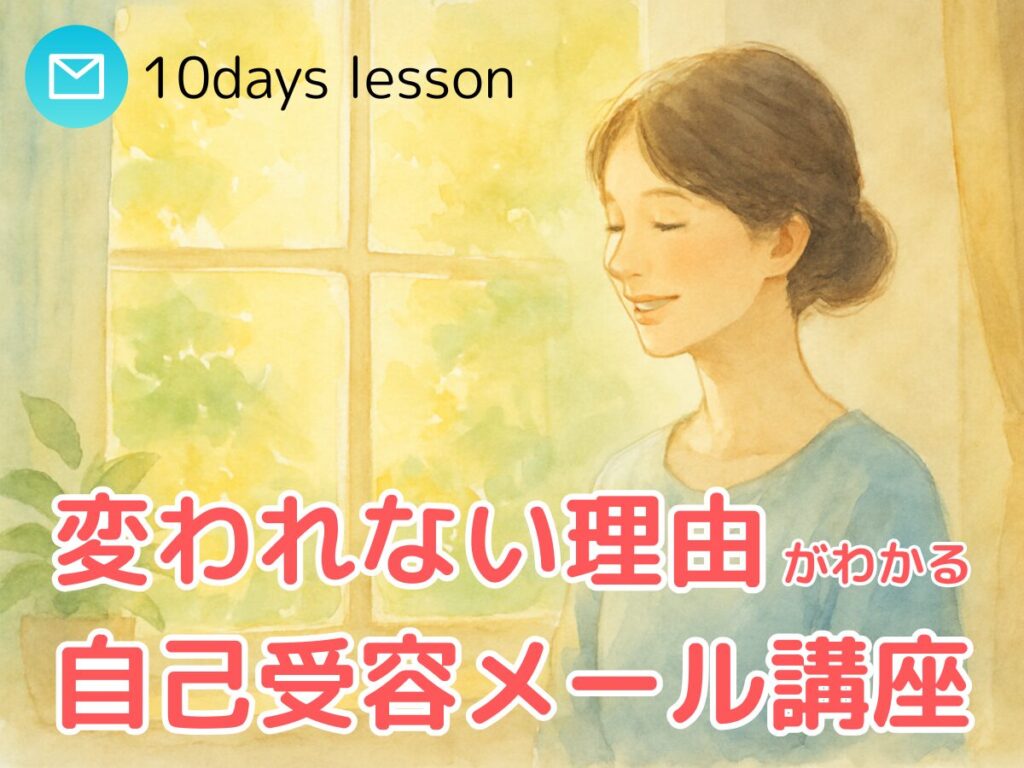
体験セッション
一人ではたどり着きにくい心の奥へ、そっと寄り添ってみませんか。
あなた自身を、もっと自由に、もっと軽やかに生きるために。
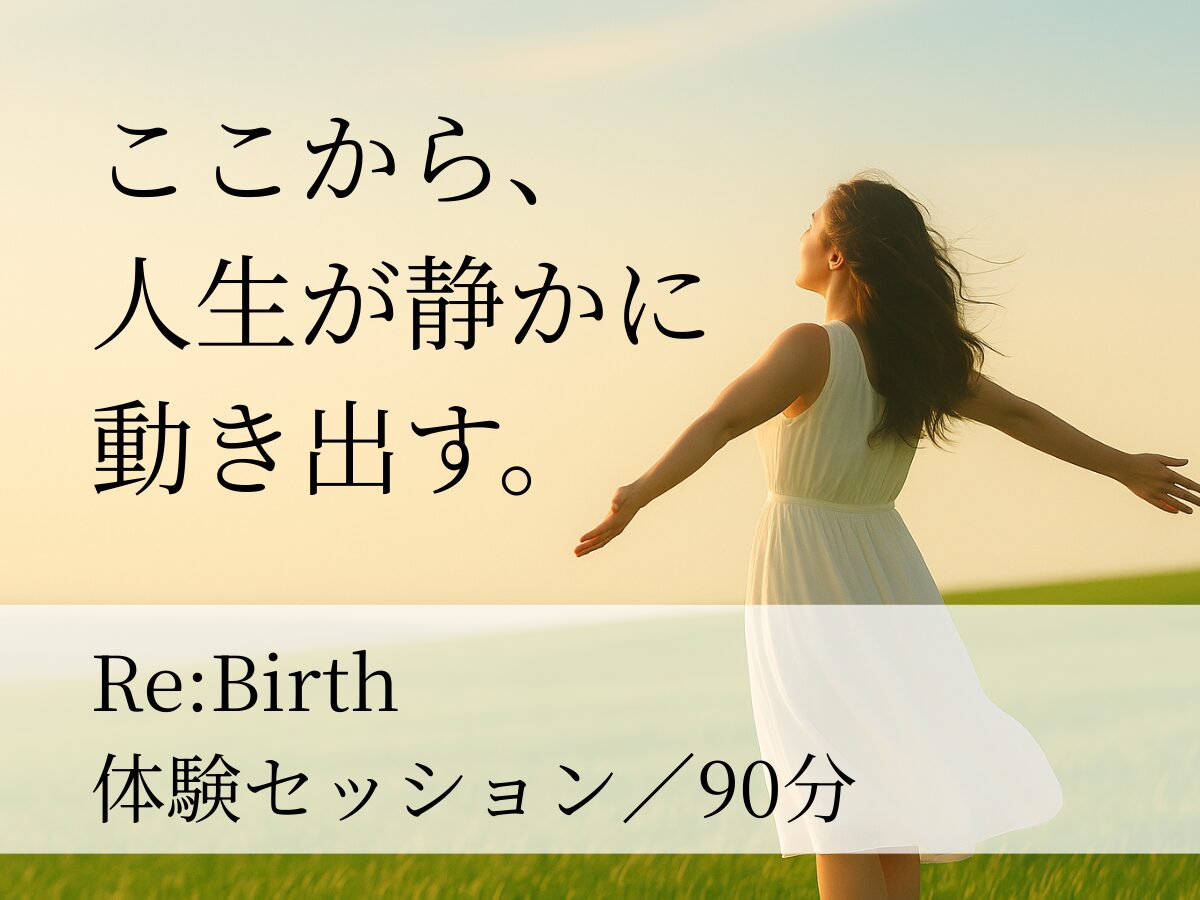
最後までお読みくださりありがとうございます^^