一帯一路より巧妙な支配──IMFと財務省が仕掛ける「緊縮という植民地化」

「一帯一路は危険だ」と日本のニュースではよく言われます。たしかに、中国がアジアやアフリカ諸国に巨額のインフラ投資を持ちかけ、その見返りに港や資源を奪っていく手法は、あからさまな経済的支配と言えるかもしれません。
でも実は、それよりもはるかに巧妙で、静かに、しかも抵抗されにくいかたちで国を支配する仕組みがあります。
それが、IMF(国際通貨基金)と日本の財務省が連携して進めてきた「緊縮という名の構造的支配」です。
なぜか「国民のためになっていない」政策ばかり
消費税は上がる一方で、法人税は引き下げられ、社会保障は「将来のため」と言われながら削られていく。
財政が苦しいというわりに、トマホークミサイルや海外援助には兆単位のお金が簡単に出ていく。
どう考えても、私たち一般庶民のために政治が動いているようには思えない。
この違和感の正体は、「国民の豊かさより、財政の引き締めが優先される」という発想にあります。これが、財務省とIMFが共有している“緊縮思想”です。
IMFと財務省──グローバル緊縮同盟
IMFは、危機に陥った国々に「財政再建プログラム」として緊縮政策を課すことで知られています。年金削減、医療費の自己負担増、公務員の削減、国有企業の民営化など、国力を下げることで、アメリカが支配しやすい構造に変えていくのです。
そして驚くべきことに、日本の財務省もまったく同じ処方箋を自国民に課してきました。
- 消費税の段階的引き上げ(5%→8%→10%、そして15%も視野に)
- 社会保障費の圧縮
- 公務員削減と非正規雇用の拡大
- 地方自治体の統廃合
これらはすべて、IMFの定めた「健全財政」のモデルとぴったり一致しています
洗練されすぎて、誰も気づけない支配構造
中国の一帯一路が「借金の罠」であるなら、IMF×財務省の緊縮は「思考の罠」と言えるかもしれません。
- 苦しくても「将来世代のため」と納得させられる
- 支援を減らされても「自己責任」と思い込まされる
- 豊かさを求めること自体が「ワガママ」とされる
こうして、国民は「自分の首を絞めている構造」に気づかないまま、静かに従わされていくのです。
緊縮は「失敗」ではなく「戦略」だった
もっとお金を使えばいいのに。
国債は自国通貨建てだから破綻はしないはずなのに。
なぜこんなに窮屈な思いをし続けなければいけないのか?
答えは簡単です。
それが、“意図された政策”だからです。
緊縮は、「間違っているから起きている」のではなく、
「誰かにとって都合がいいから続いている」。
それが、財務省とIMF、そしてその背後にある国際金融資本や米国の国益とリンクした、「構造的植民地支配」の正体なのです。
では、どうすればこの構造から抜け出せるのか?
まず第一に、「おかしい」と気づくこと。
そして、「誰の利益になっているか?」と問い直すこと。
・なぜ財務省は一貫して緊縮路線を譲らないのか?
・なぜIMFの勧告は国民の生活を苦しめるものばかりなのか?
・なぜマスコミはこれを深く報じないのか?
これらの問いに向き合うことが、私たち自身の「思考の独立宣言」になるのだと思います。
中国の支配が危険だと言うなら、
アメリカと財務省の構造的支配にも目を向けなければ、
この国の本当の主権回復はありえません。
今、私たちにできること
- この構造を「知る」こと。
- 家族や仲間と「話す」こと。
- 政治家や政策の背景に「誰が得をするか」を見ること。
- 「もう騙されない」と決めること。
この国の主権者は国民である「あなた」です。
気づいた人から、変えていくことができるはずです。
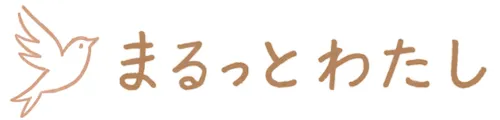


円安による企業の叩き売りで株主の株主まで含めた実質外資比率(政府の定義とは直接投資のみなので異なる)がもうすぐあるいは既に50%を超えます。一義的には金の流れが外資中心になる。主役交代。これは全部外資の手柄になるから全試合日本が負けるクソゲー化です。常に利潤のゲームで日本が負ける八百長です。成長力がなくなる。日本に投資するより外資に投資して間接的に植民地支配してもらったほうが投資家は儲かる。日本経済が終わる。かなり深刻な危機的状況です。
円安と株主構成の変化で、
利益が国内に循環しにくくなっている点は確かに重要ですね。
ただ、それは「外資が悪い」というより、
国内に再投資させる仕組みや税制、賃金政策を
設計してこなかった国家の問題だと私は考えています。
恐怖で語ると全体が見えなくなるので、
構造としてどこを変えれば循環が戻るのか、
そこを一緒に考えたいですね。